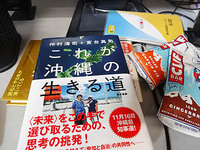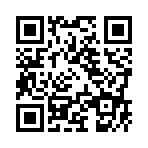クライミング関連
梅雨の日に考える
某フリーファン誌が柘植氏が書いている、クライミング用語解説が結構好きです。
今回は「人工壁」でした。ウチのジムでは、まだクライミングを始めて間もない方が多く、外でクライミングする人のほうがどちらかというと少ない状態。そんな中よく「外の岩がやっぱりいいよ。」って意見をよく聞きます。そのあたり私も引っかかるものがあったのですが、見事に柘植氏が書き上げています。ま、私の言葉で言えば、とにかく「お外でいろんな岩でいろんなとこで岩登りすること」が楽しいということなのだろうか?岩登り自体は外だろうと中だろうと同じだし。

さてさて、そこに柘植氏も最後に書いてあるように、大切なことは「自然壁で登るときは自然の岩を登る意味というのを考えたほうがいいと思う。・・・(中略)人工壁で可能なこと、を逆に考えるとおのずとその答えは似かよってくるような気がする。多分、100年後のクライミングスタイルはそこにあると思う。」と書いて〆てますが、いい得て妙です。100年後というよりもっと近い先かもしれませんが。
また、某ロクスノの031号のOBGで杉野氏も「クライミングは未来永劫続いていくだろう。しかしそれが文化として成り立ち続けるかどうかは、拓く側がどれだけどのことを理解するかにかかっている。 今まで積み上げてきたことを押しつぶしてしまうことないよう、登る側も、もっと知るべきことがある。」と〆てあります。うん、なるほど。
奇抜な行為は、たまに誤解と問題を招くことがあるとは思います。それは、今のモラルとあわなくとも、もしかしたら、近い将来当たり前になることさえあるかと。しかし、その行為が、上記の二人のいうところの「見性」があれば、決してつまらないものにならないと思います。しかし、それが「見性」なく程度(文化度)の低い行為であり、そしてまたそれが受けいられるような、クライミング界であれば、少なくとも私にとってはつまらない世界になるかもしれません。「岩と雪」169号に草野氏が書いてあることはその表れの一つではないかと、あらためて感じます。
なかなか、私自身、過去を回顧していくなかで、その「見性」を見誤ったことも多く、反省してますが、考える時間だけは人一倍かけたかな?っと思います(言い逃れではありません)。先人達の行為が、いかに素晴らしかったからこそ、今も、なんだかんだとクライミングが楽しいものであってっくれているものだと感じます。改めて、勉強しなおさなくてはなりませんね。
今回は「人工壁」でした。ウチのジムでは、まだクライミングを始めて間もない方が多く、外でクライミングする人のほうがどちらかというと少ない状態。そんな中よく「外の岩がやっぱりいいよ。」って意見をよく聞きます。そのあたり私も引っかかるものがあったのですが、見事に柘植氏が書き上げています。ま、私の言葉で言えば、とにかく「お外でいろんな岩でいろんなとこで岩登りすること」が楽しいということなのだろうか?岩登り自体は外だろうと中だろうと同じだし。

さてさて、そこに柘植氏も最後に書いてあるように、大切なことは「自然壁で登るときは自然の岩を登る意味というのを考えたほうがいいと思う。・・・(中略)人工壁で可能なこと、を逆に考えるとおのずとその答えは似かよってくるような気がする。多分、100年後のクライミングスタイルはそこにあると思う。」と書いて〆てますが、いい得て妙です。100年後というよりもっと近い先かもしれませんが。
また、某ロクスノの031号のOBGで杉野氏も「クライミングは未来永劫続いていくだろう。しかしそれが文化として成り立ち続けるかどうかは、拓く側がどれだけどのことを理解するかにかかっている。 今まで積み上げてきたことを押しつぶしてしまうことないよう、登る側も、もっと知るべきことがある。」と〆てあります。うん、なるほど。
奇抜な行為は、たまに誤解と問題を招くことがあるとは思います。それは、今のモラルとあわなくとも、もしかしたら、近い将来当たり前になることさえあるかと。しかし、その行為が、上記の二人のいうところの「見性」があれば、決してつまらないものにならないと思います。しかし、それが「見性」なく程度(文化度)の低い行為であり、そしてまたそれが受けいられるような、クライミング界であれば、少なくとも私にとってはつまらない世界になるかもしれません。「岩と雪」169号に草野氏が書いてあることはその表れの一つではないかと、あらためて感じます。
なかなか、私自身、過去を回顧していくなかで、その「見性」を見誤ったことも多く、反省してますが、考える時間だけは人一倍かけたかな?っと思います(言い逃れではありません)。先人達の行為が、いかに素晴らしかったからこそ、今も、なんだかんだとクライミングが楽しいものであってっくれているものだと感じます。改めて、勉強しなおさなくてはなりませんね。